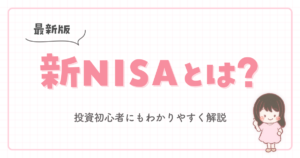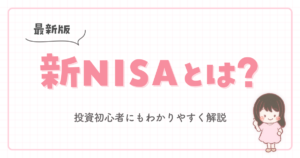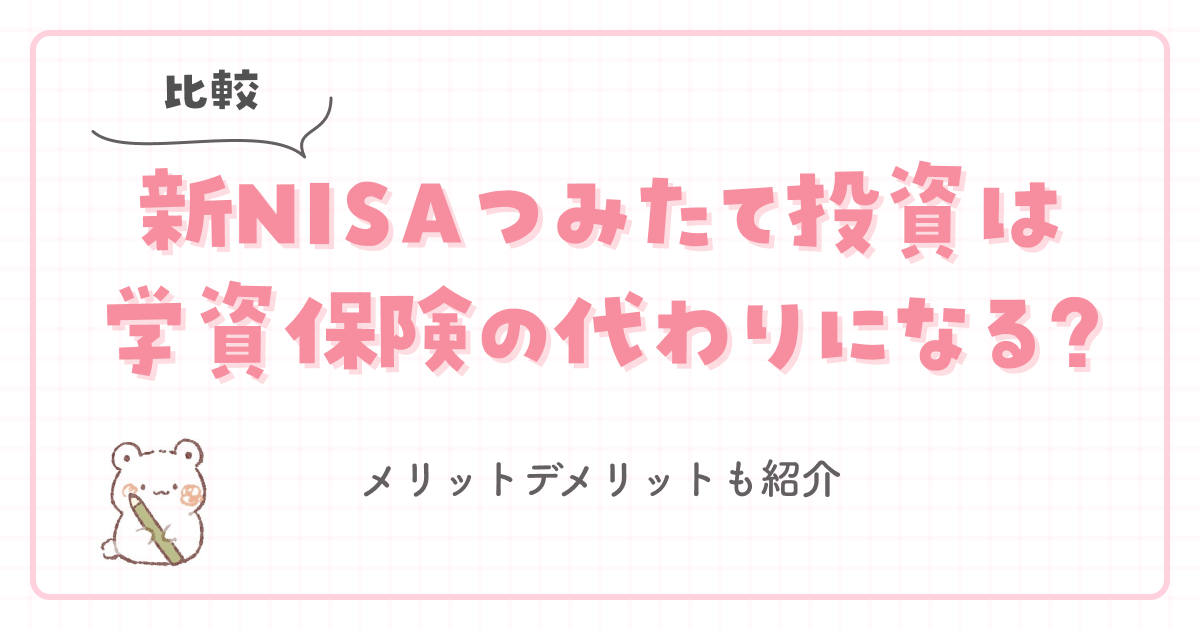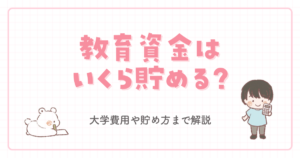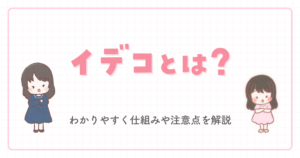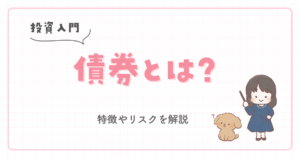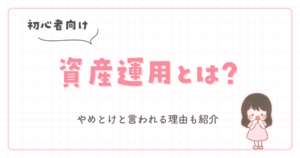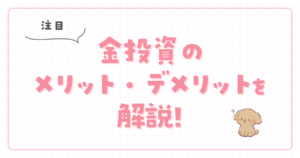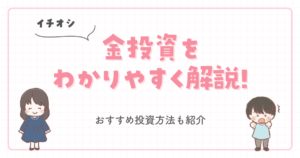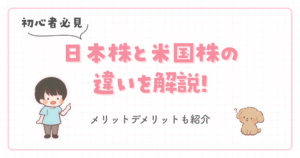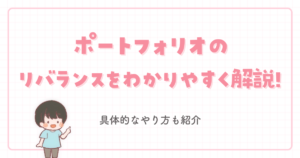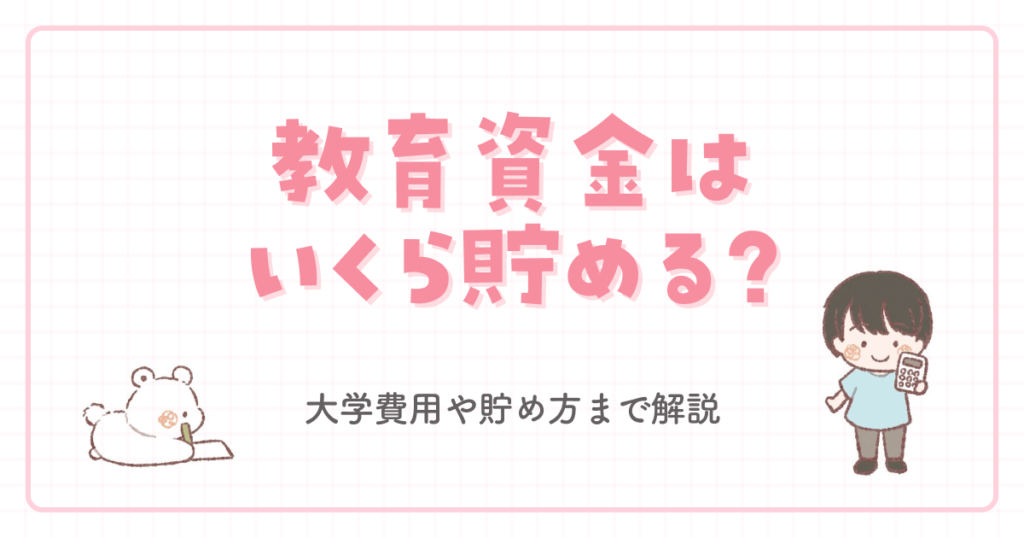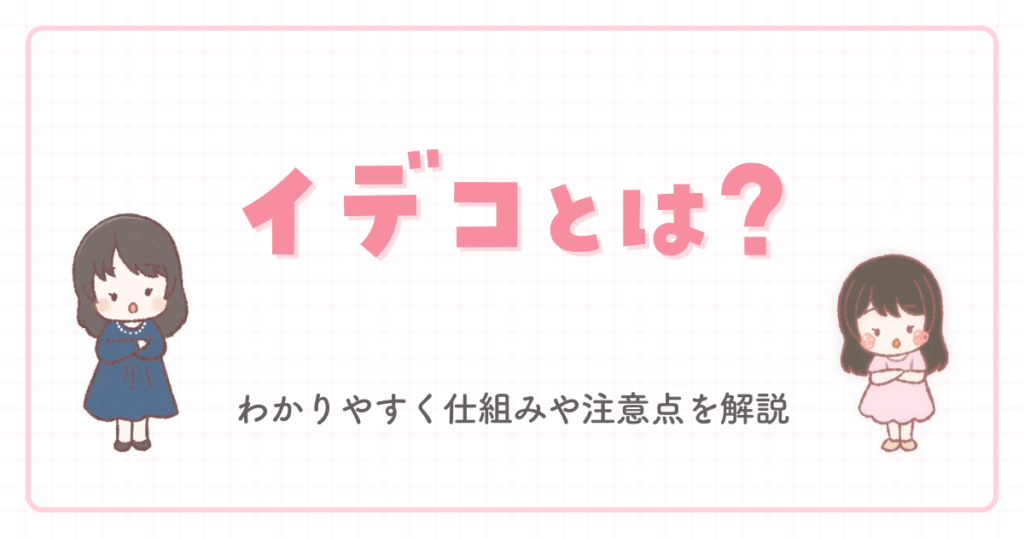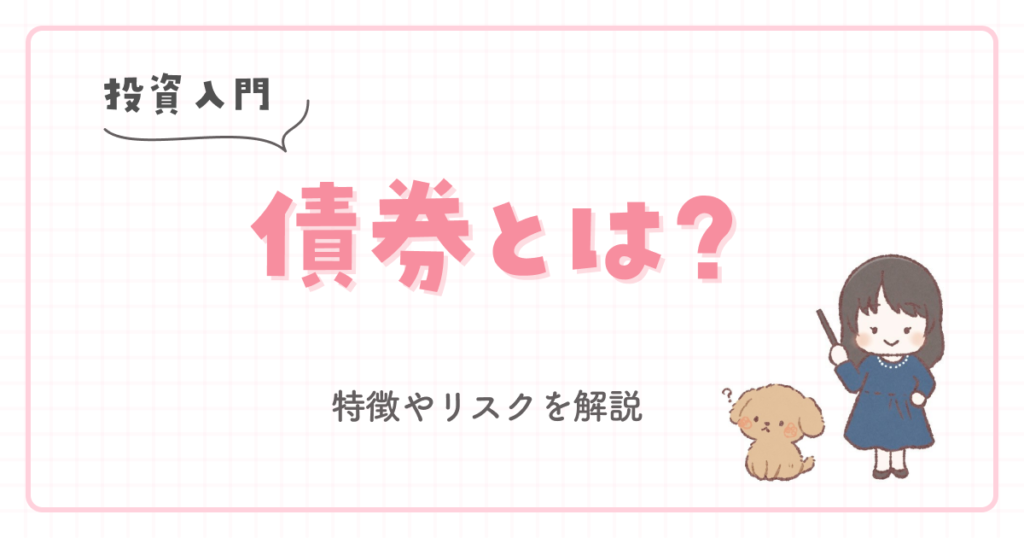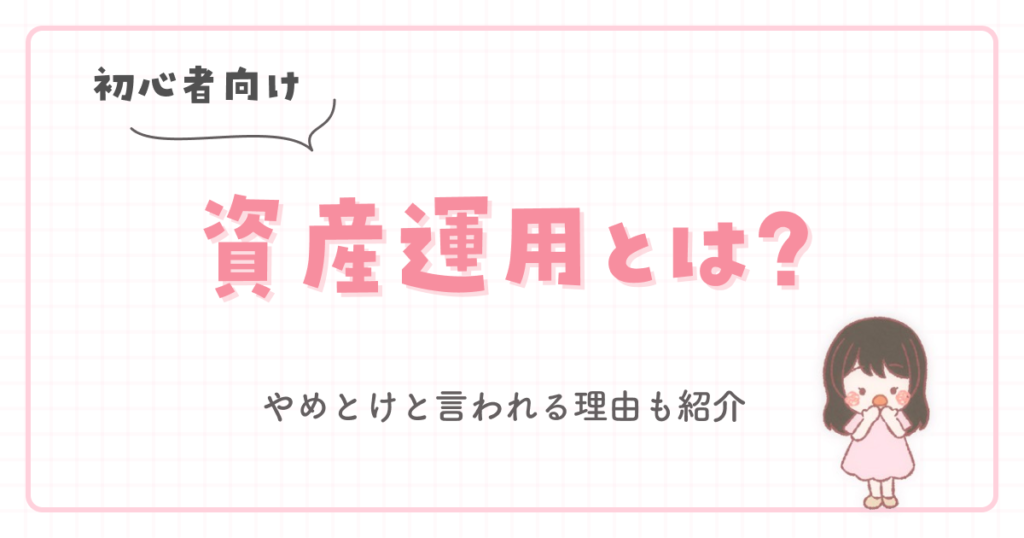この記事では、新NISAつみたて投資は学資保険の代わりになるのか?という疑問にお答えします。
また、新NISAと学資保険のメリットとデメリットについても、わかりやすく説明します。

新NISAのつみたて投資は、
学資保険の代わりになるの?



教育資金の準備方法は、
どちらを選べばいいの?



結論から言うと、
新NISAのつみたて投資は
学資保険の代わりになります。
新NISAは運用益が非課税で、必要なときに引き出せる柔軟性があります。
また、長期運用により学資保険を上回るリターンが期待できるためです。
学資保険には、大学進学や留学費用など将来の教育資金を貯める機能と保険としての機能という2つの役割があります。
返戻率が確定している学資保険は、満期時に受け取れる金額があらかじめ決まっており、確実にお金が戻ってくる仕組みです。
返戻率(へんれいりつ)とは
払い込んだ保険料の総額に対して、満期時などに受け取れる金額の割合。
100%を超えると利益が出る。
そこで、教育資金の準備を検討している方に向けて、新NISAと学資保険の特徴や違いについて詳しく解説します。



子どもの将来のために、最適な資金準備方法を見つける参考としてください!
▶︎気になる項目をタップすると、すぐに該当箇所を読めます。
新NISAつみたて投資は学資保険の代わりになります


新NISAのつみたて投資は、教育資金の準備方法として学資保険の代わりとして活用できます。
学資保険は子どもの教育資金を確実に準備する手段として多くの家庭で利用されてきました。
しかし、低金利時代のいま、学資保険の返戻率は100%をわずかに上回る程度で、インフレに対応しきれない可能性があります。
新NISAつみたて投資なら、長期運用による資産成長が期待でき、運用益も非課税となるため、より効率的に教育資金を準備できます。
新NISAと学資保険には、それぞれ異なった特徴や仕組みがあるので、詳しく見ていきましょう。



下記の表で比較しています。
| 学資保険 | 新NISA | |
|---|---|---|
| 元本保証 | あり (途中解約すると 元本割れする可能性) | なし (長期投資で安定傾向) |
| 出金の自由度 | 低い | 高い |
| 積立金額の 変更 | できない | できる |
| 税制優遇 | 生命保険料の控除 | 運用益が非課税 |
| 収益性 | 低い | 運用成績による |
| 契約できる人 | 子ども(0~6歳)の 保護者 | 18歳以上 |
新NISAと学資保険の違いを見ていきましょう。
新NISA
新NISAは投資で得た利益が非課税になるため、効率的に資産形成できる制度です。
運用益が非課税なため、利益をそのまま投資に回すことで複利の力を加速させ、資産を雪だるま式に増やせる可能性があります。
複利とは?
元本だけでなく、これまでに得た利息にもさらに利息がつく仕組みのこと
投資の性質上、運用による損失の可能性はありますが、長期間にわたり積み立て投資を行うことでリスクを抑えられます。
学資保険
学資保険とは、教育資金を計画的に準備できる保険商品です。
毎月定められた金額を掛金として支払うことで、契約時に決められた金額を受け取れます。



元本が保証されているため、
損失リスクが低いのが特徴です。
新NISAのメリット・デメリット
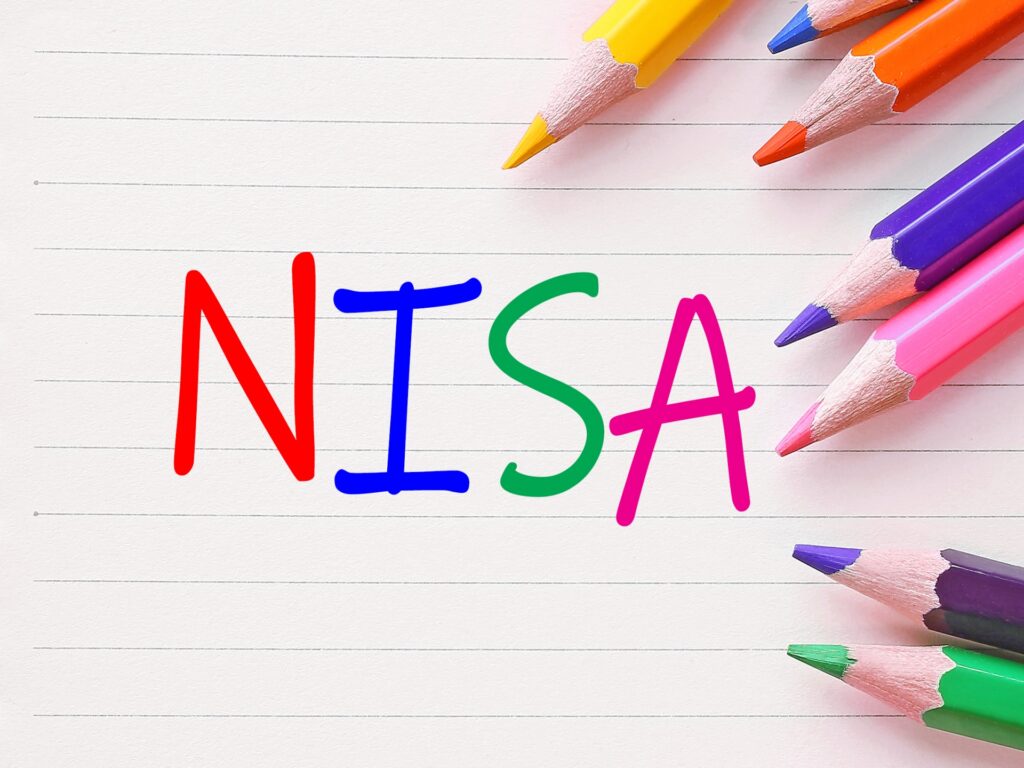
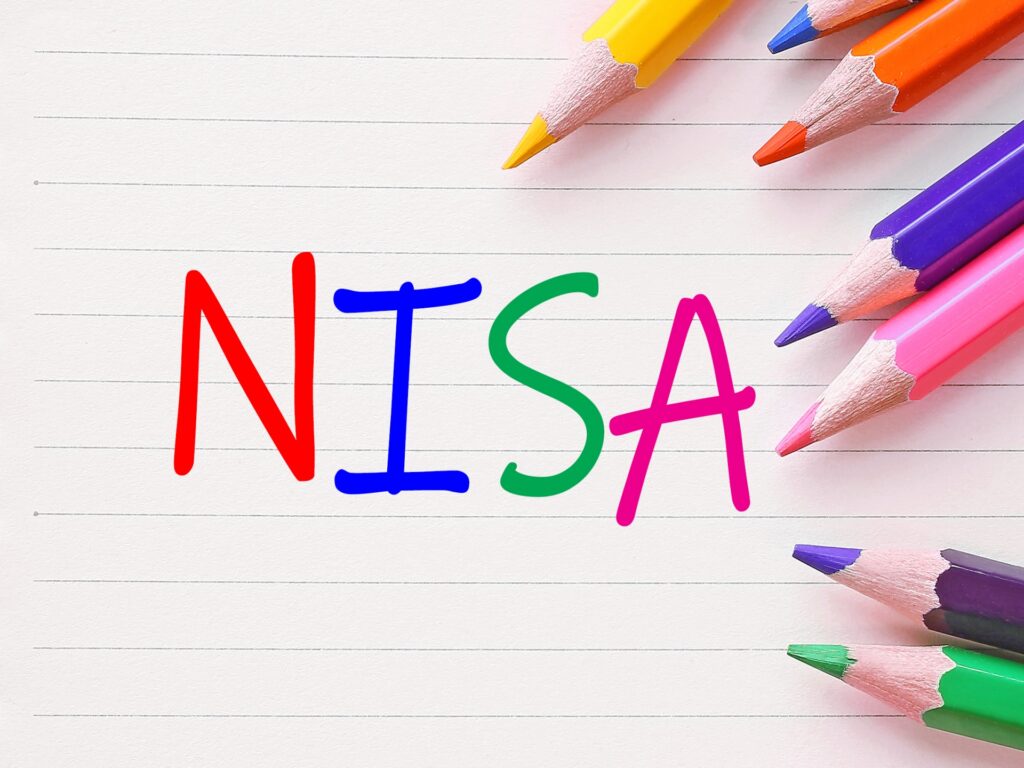
ここでは、新NISAのメリットとデメリットを紹介します。



それぞれ見ていきましょう。
新NISA4つのメリット


新NISAの4つのメリットは以下の通りです。
1.好きなときに現金化できる
学資保険は満期まで待たなければなりませんが、新NISAなら急な教育費が必要になったときでもすぐに売却して現金化できます。



原則、数日から1週間ほどで現金化できますよ。
教育費が必要になるのは入学時だけでなく、習い事や留学など、さまざまな場面があります。
のため、状況に応じて出金できるのは、心理的にも安心できるポイントです。



基本的に急な出費にも対応できる
2.つみたてる金額を変更できる
新NISAは、家計の収支状況にあわせて積立額を変更できます。
金融機関によって最小金額は異なりますが、100円から10万円まで自由に積立額を調整できます。
資金に余裕があるときは積立額を増やし、余裕がないときは減らすことができます。



家計的にも心理的にも負担が
軽くなりますね!
3.売却益や配当金を非課税で受け取れる
新NISAの最大のメリットは、運用益(配当金や売却益)を非課税で受け取れることです。
通常口座の投資では、投資信託や株の利益に対して、通常は20.315%の税金がかかります。
※税金20.315%の内訳
所得に関係なく、所得税は15%、住民税は5%、さらに2037年までは復興特別所得税が所得税額の2.1%加算されます。
そのため、全部で15%+5%+0.315%(15%x2.1%)=20.315%かかります。
参照:金融庁公式サイト
ですが、新NISA口座で運用すると、投資で得た利益に税金はかかりません。
例えば
100万円の利益が出た際、通常は約20万円の税金がかかり、手取り額は80万円になります。
100万円(運用益)ー 20万円(税金)
=80万円(手取り額)



手取りが20万円も減ってしまいます…。
しかし、新NISA口座内であれば運用益に対して非課税なので、手取り額は100万円になります。



非課税のメリットって、
大きいですね!
4.運用成果次第で資金を増やせる
新NISAのつみたて投資では、金融商品に投資するので運用の成果次第で、資金を増やせる可能性があります。
過去の実績では、長期投資により年率3~7%ほどのリターンが期待できます。



基本的に学資保険の返戻率を大きく上回る数字!
新NISA3つのデメリット
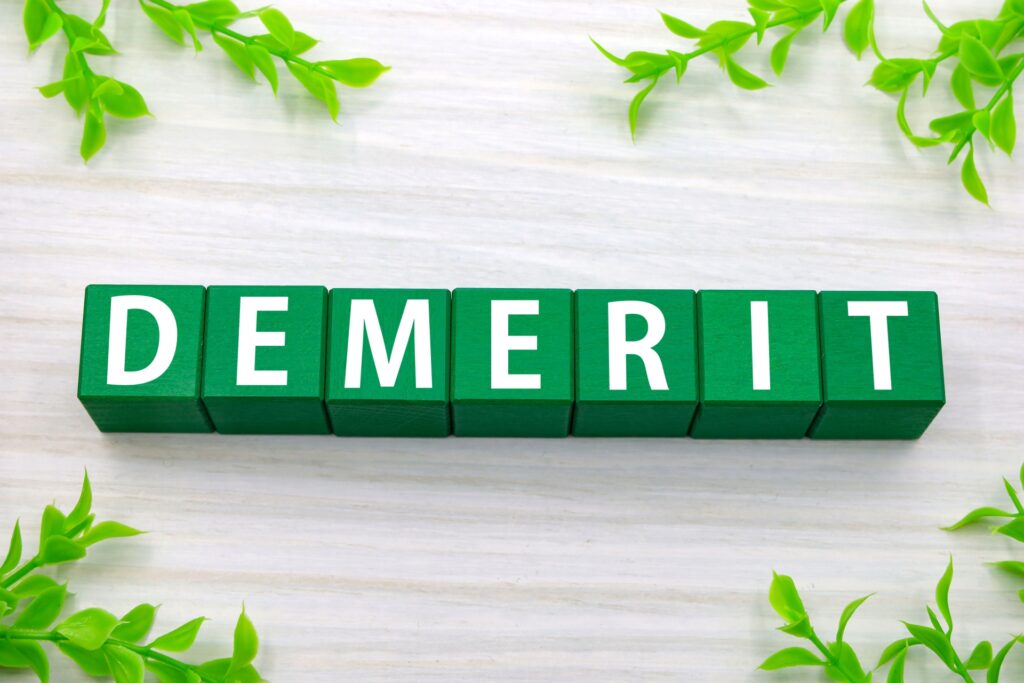
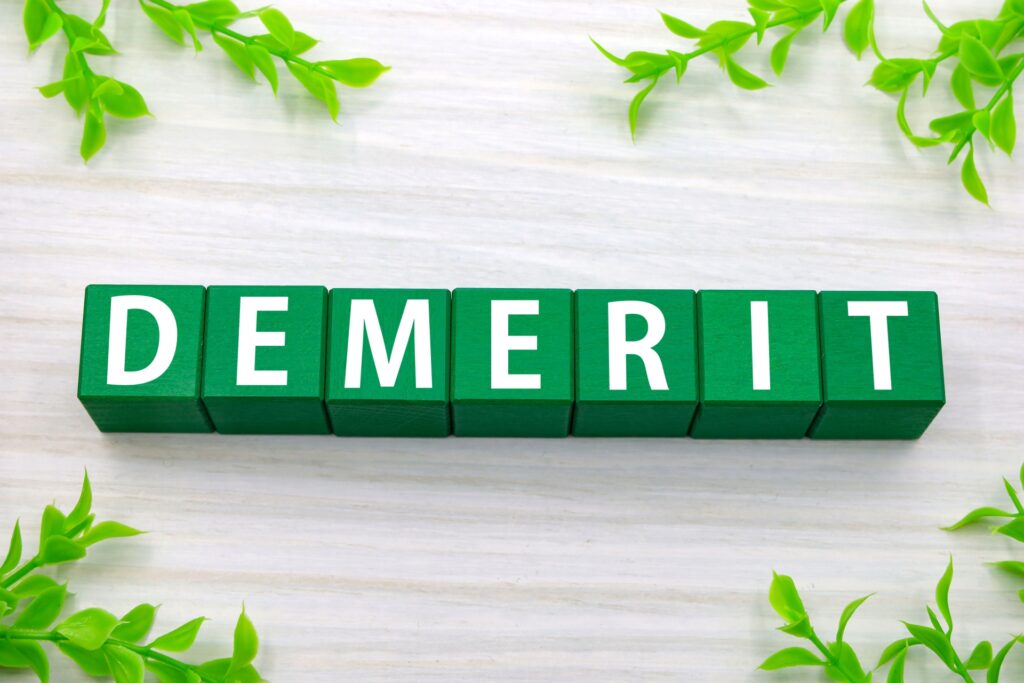
ここでは、新NISA3つのデメリットを説明します。
1.元本保証がない
投資信託の価格は日々変動するため、教育資金が必要なタイミングで相場が下落していると、元本割れする可能性があります。
学資保険なら契約時に返戻率が確定しているため、確実に受け取れる金額がわかりますが、新NISAでそのような保証はありません。



投資の性質上、元本割れを起こすリスクはあります!
しかし、長期運用によって購入価格を平均化することで、元本割れのリスクを低くできます。
この投資方法はドルコスト平均法の効果によるものです。
ドルコスト平均法とは?
一定期間ごとに一定金額で同じ投資商品を継続的に購入する投資手法のこと



教育資金は長期に渡ってつみたてていくから、リスクは軽減されます。
ドルコスト平均法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
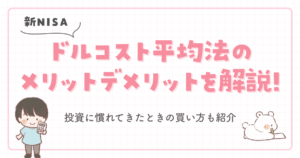
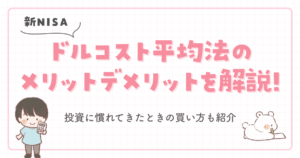
2.所得控除(しょとくこうじょ)・損益通算(そんえきつうさん)がない
学資保険で払った保険料は所得控除の対象ですが、新NISAは投資したお金が控除の対象にはなりません。
また、損失が出ても他の投資の利益と相殺することもできません。
新NISAのメリットは、運用益に税金がかからない点に限られているため、毎年の税金を減らせるわけではない点に注意が必要です。



新NISAが節税になると言われるのは、運用益に税金がかからない点です。
所得控除(しょとくこうじょ):課税対象となる所得から、一定の金額を差し引ける仕組み
損益通算(そんえきつうさん):利益と損失を相殺すること
3.運用商品が限られる
新NISAつみたて投資枠で購入できるのは、金融庁が定めた一定の基準を満たす金融商品に限定されています。



長期・分散投資に適した投資信託とETFに限定されています!
そのため、幅広い商品に投資したい人は物足りなさを感じるかもしれません。
一方で、商品が厳選されている分、初心者でも選びやすく、長期的に安定した資産形成を目指す人には利用しやすい面もあります。



投資初心者にとっては、
質の低い商品を選んでしまうリスクが軽減されています。
学資保険のメリット・デメリット
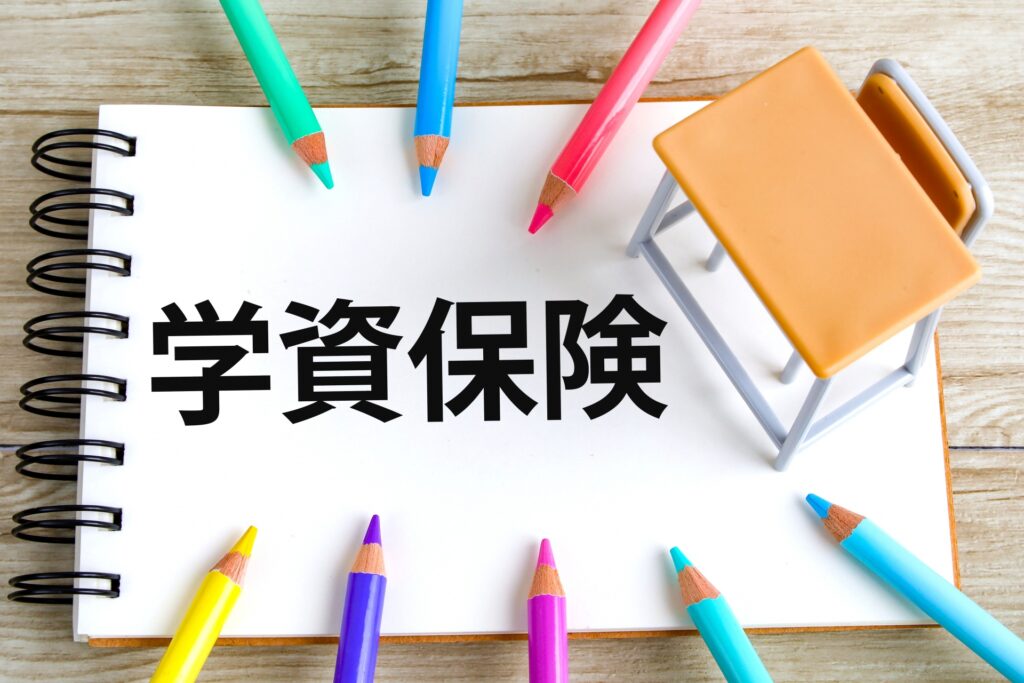
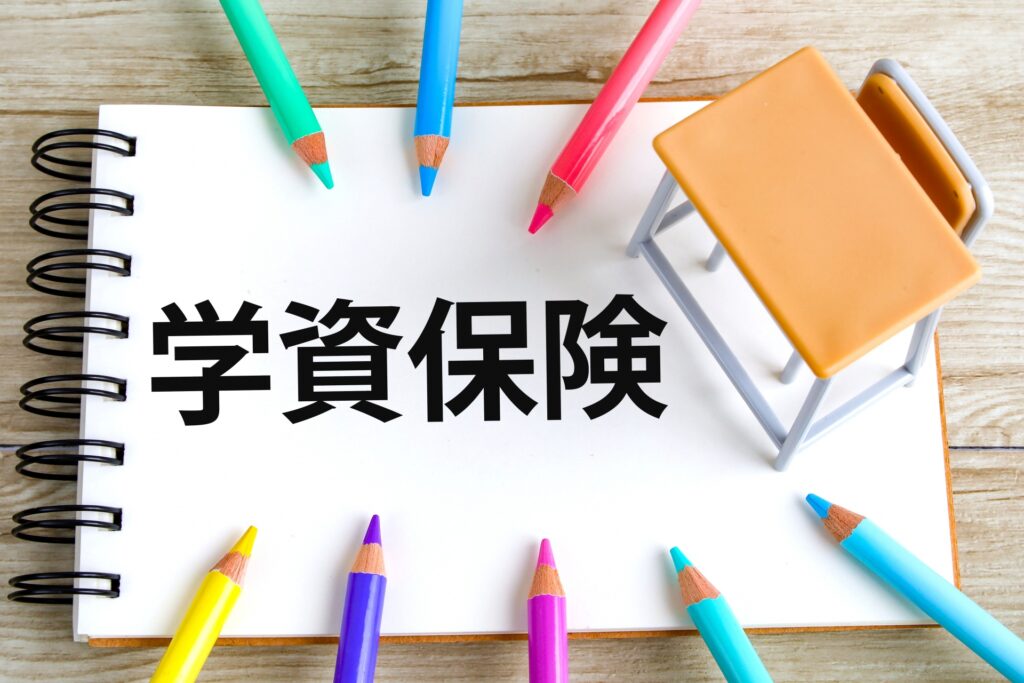
ここでは、学資保険のメリットとデメリットを紹介します。



人気の学資保険のメリット・
デメリットをしっかり解説します。
学資保険3つのメリット


子どもが生まれたら多くの人が考える学資保険。
ここでは、学資保険のメリットを紹介します。
1.教育資金の計画を立てやすい
学資保険は、以下の内容が契約時に定められているため、資金計画を立てやすいのが特徴です。
- 払込期間
- 受け取り時期
- 受け取り金額
また、元本保証されているので、リスクなく必要な教育資金をつみたてられます。



受け取り金額が決まっているため、ライフプランが立てやすいですね。
2.万が一のとき保険料が免除される
保険料を払い込む契約者に万一のことがあった場合、それ以降の保険料は免除されて、教育資金を受け取れます。
これは、学資保険の保険料払込免除特約(ほけんりょうはらいこみめんじょとくやく)による仕組みです。
保険料払込免除特約は、具体的には契約者が以下のような状態になった場合、適用されます。
- 死亡したとき
- 高度障害状態に該当したとき
- 不慮の事故により所定の身体障害の状態に
該当したとき



学資保険には、保険としての
機能も備わっています。



保険料払込免除特約は、ほとんどの学資保険には付加されています。
上記に該当した場合でも、保障は継続され、祝金や満期保険金を受け取れます。
満期保険金とは
学資保険などで、満期時に被保険者(子ども)の教育資金として受け取れるお金。



万が一の事態が起きても、
教育費を確保できるのは安心ですね。
3.生命保険料控除になる
学資保険は、払い込んだ保険料が生命保険料控除の対象となるため、税制上の優遇を受けられます
そのため、確定申告することで、所得税や住民税の税負担を軽減できるのです。



所得税は最大で4万円、
住民税は最大で2.8万円の
所得控除を受けられます。
学資保険3つのデメリット


メリットの多い学資保険ですが、デメリットもあります。
詳しく見ていきましょう。
1.途中解約すると、元本割れする可能性が高い
学資保険は、原則18歳になるまで引き出せない契約が多いです。
途中解約すると解約返戻金が払込保険料を下回ることがほとんどです。
契約から10年以内に解約した場合、払い込んだ保険料の70%を下回って戻ってくるケースも多々あります。



一度契約すると、満期まで持たないと損になるんですね。
家計の急変や転職による収入減少、子どもの進路変更など、予期せぬ事情で保険料の支払いが困難になることもあります。
しかし、解約すれば大きな損失となるため、継続するか解約するかの判断が難しいです。



さまざまなケースを検討した上で、加入を検討しましょう!
解約すると同時に保険の保障もなくなりますので、ご注意ください。



学資保険は、柔軟性に欠ける点もあります。
2.課税対象となる可能性がある
学資保険の保険金を受け取る際には、課税されることがあります。
具体的には、払い込んだ保険料の総額に対して、50万円以上の利益がある場合です。
この場合、一時所得とみなされ、課税の対象になる可能性があります。
契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象となり、より高い税率が適用される可能性もあります。



一方、新NISAは完全に非課税となります。
3.インフレのリスクがある
学資保険のデメリットとして、インフレに弱いことも挙げられます。
インフレ(インフレーション)とは?
物価の上昇によって、お金の価値が下がってしまうこと
学資保険は契約時に将来受け取る金額が固定されるため、物価上昇に対応できません。
現在の学資保険の返戻率は100〜105%程度と低いため、18年後の物価を考慮すると、実質的な価値が目減りする可能性が高いです。
たとえば
年2%のインフレが続いた場合、18年後の物価は約1.4倍です。
300万円の満期金の実質的な価値は、現在の約210万円程度まで下がることになります。



大学の授業料は過去30年で
約1.5倍に上昇しています!
現在の国立大学の授業料は年間約54万円ですが、18年後には80万円を超える可能性もあります。
そのため、長期的にはインフレを上回るリターンが期待でき、物価上昇に対応した教育資金の準備が可能です。
新NISAつみたて投資枠について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
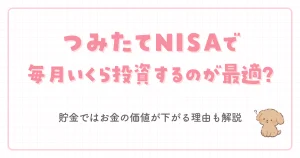
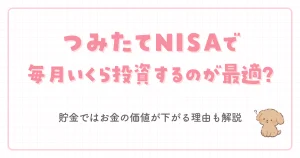
新NISAつみたて投資は学資保険の代わりになる|まとめ


新NISAのつみたて投資は、学資保険の代わりとして教育資金を準備する有効な選択肢となります。
新NISAと学資保険には、それぞれ異なる特徴があり、家庭の状況や考え方によって最適な選択は変わります。
新NISAのメリット・デメリット
新NISAは運用益が非課税で、必要なときにいつでも引き出せる柔軟性があり、長期運用により高いリターンが期待できます。
学資保険のメリット・デメリット
学資保険は元本保証があり、返戻率が確定している安心感と、万が一の際の保障機能を備えています。
どちらを選ぶかは、リスク許容度や家計の状況、教育資金の目標額などを総合的に考慮して決めることが大切です。
インフレが進んで物価が上昇すると、お金の価値は徐々に下がってしまいます。
長期的にはインフレを上回るリターンが期待できる、新NISAつみたて投資による教育資金の準備がおすすめです!
新NISAは、長期運用することで元本割れのリスクを低く抑えながら、資産を増やせる可能性があります。



積立額を変更したり、自由に現金化できるため、無理なく投資を続けられる点も魅力です。



新NISAを活用して、自分のペースで教育資金を築きましょう。
新NISAについては、こちらの記事で詳しく説明しています。